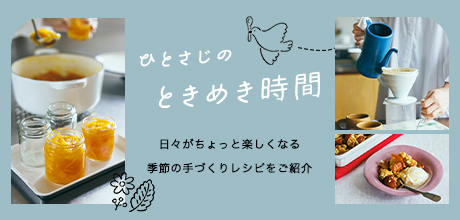手作り 少量みそ【動画あり】

作りやすく、失敗の少ない少量仕込み!
監修:株式会社伊勢惣
材料【でき上がり約800g分】
| 大豆 | 200g |
|---|---|
| 乾燥米こうじ | 200g |
| 塩 | 90g |
| 種みそ(※) | 適宜(入れる場合は60g) |
| ※原材料に「アルコール」や「酒精」がない、酵母菌が生きているもの。昨年手作りしたみそでも | |
| 除菌用のアルコール(※) | 適量 |
| ※焼酎やホワイトリカーなどアルコール35度以上のもの(キッチン用のアルコールスプレーは避ける) | |
| ▼倍量で作る場合 各材料を倍にして仕込んでください。 | |
| 【準備する道具】 | |
| ・保存容器(1L以上のもの) | |
| ・こうじと塩を混ぜるためのボウル | |
| ・大豆を煮るための鍋、ざる(ともに直径20cm前後) | |
| ・大豆をつぶすための厚手の耐熱性ポリ袋とめん棒(熱々の大豆をつぶすのでふきんを挟むのがおすすめ)、またはボウルとマッシャー | |
| ・ラップ | |
| ・重石用の塩(重石をする場合、240g程度・でき上がりの30%。ポリ袋に入れて使用) | |
| ・保存容器を入れる紙袋または、覆うための新聞紙(透明容器の場合。ホーロー容器などの場合は必要ありません) | |
| ▼倍量で作る場合 保存容器は2L以上のもの。鍋、ざるは直径24cm程度がおすすめです。重石用の塩は倍量にしてください。 |
作り方
1
●作る前日に
みそを仕込む前の晩に大豆を洗い、大豆の3~4倍以上の水にひと晩(約12時間)ひたす。
※夏場は冷蔵室に入れる。
みそを仕込む前の晩に大豆を洗い、大豆の3~4倍以上の水にひと晩(約12時間)ひたす。
※夏場は冷蔵室に入れる。

大豆は吸水すると、約2倍の大きさになります。
2
●保存容器の内側と道具を除菌
アルコールをふきんなどに含ませ、保存容器の内側をふいて除菌する(その前に熱湯消毒をしておくとさらに安心)。ざる、ボウル、マッシャーなども除菌しておくとよい。
アルコールをふきんなどに含ませ、保存容器の内側をふいて除菌する(その前に熱湯消毒をしておくとさらに安心)。ざる、ボウル、マッシャーなども除菌しておくとよい。
3
●新しい水に替えて大豆を煮る
鍋に水けをきった大豆と新しい水(大豆の2倍の量)を入れ、火にかける。途中アクをとり、湯を足しながら3~5時間、弱火で煮る。大豆の皮が入っていてもOK。
※圧力鍋で煮る場合は、圧を抜くところに大豆の皮などが詰まると危険なので、要注意。
鍋に水けをきった大豆と新しい水(大豆の2倍の量)を入れ、火にかける。途中アクをとり、湯を足しながら3~5時間、弱火で煮る。大豆の皮が入っていてもOK。
※圧力鍋で煮る場合は、圧を抜くところに大豆の皮などが詰まると危険なので、要注意。

親指と小指でつぶせるくらいのやわらかさになれば煮上がり。

4
●ゆでた大豆の煮汁をきる
(3)が熱いうちにざるにあげ、煮汁をきる。このとき、煮汁を全部捨てずに種水用として150ml程度取りおく。
▼倍量で作る場合
煮汁を300ml取りおく。
(3)が熱いうちにざるにあげ、煮汁をきる。このとき、煮汁を全部捨てずに種水用として150ml程度取りおく。
▼倍量で作る場合
煮汁を300ml取りおく。

煮汁の取りおきを忘れずに。

5
●「塩切りこうじ」を作る
除菌したボウルにこうじ、塩を入れて両手で下からすくい上げながら、すり合わせるようにしてよく混ぜる。
除菌したボウルにこうじ、塩を入れて両手で下からすくい上げながら、すり合わせるようにしてよく混ぜる。

空気に触れさせることでこうじ菌の働きが活発に。
6
●「塩切りこうじ」をふやかす
人肌程度(30℃くらい)にさました(4)の種水(90ml)を(5)の塩切りこうじに入れて混ぜ、そのまま10分ほどおいてなじませる。熱いとこうじ菌が死んでしまうので注意。
▼倍量で作る場合
種水(180ml)を混ぜる。
人肌程度(30℃くらい)にさました(4)の種水(90ml)を(5)の塩切りこうじに入れて混ぜ、そのまま10分ほどおいてなじませる。熱いとこうじ菌が死んでしまうので注意。
▼倍量で作る場合
種水(180ml)を混ぜる。

7
●大豆を熱いうちにつぶす
厚手のポリ袋に(4)の大豆を入れ、熱いうちにめん棒や手などでペースト状につぶす。さめるとつぶれにくくなるので注意。熱いので、ポリ袋の上にふきんなどを敷いて、その上から作業するとよい。
厚手のポリ袋に(4)の大豆を入れ、熱いうちにめん棒や手などでペースト状につぶす。さめるとつぶれにくくなるので注意。熱いので、ポリ袋の上にふきんなどを敷いて、その上から作業するとよい。

ボウルとマッシャーでもOK。

8
●「大豆」「塩切りこうじ」「種みそ」を混ぜる
(7)の大豆が人肌くらいにさめたら、(6)、種みそ(入れる場合)を入れて、よく混ぜ合わせる。こうじをつぶさないようにやさしく。
(7)の大豆が人肌くらいにさめたら、(6)、種みそ(入れる場合)を入れて、よく混ぜ合わせる。こうじをつぶさないようにやさしく。

粘土くらいのかたさに。もし、かたい場合は、(4)で取りおいた種水を大さじ1ずつ入れて調整しましょう。

9
●「みそ玉」を作る
(8)を4~6等分して、だんご状のみそ玉にする。みそ玉にして容器に詰めると空気が抜けるので、雑菌の繁殖防止に。
▼倍量で作る場合
(8)を8~12等分して、みそ玉にする。
(8)を4~6等分して、だんご状のみそ玉にする。みそ玉にして容器に詰めると空気が抜けるので、雑菌の繁殖防止に。
▼倍量で作る場合
(8)を8~12等分して、みそ玉にする。

容器に詰めるときに空気が抜けやすくなるように、少しやわらかめに握るのがコツ。
10
●保存容器に詰める
みそ玉を容器に1~2個ずつ詰めて上から手のひらや甲で押してしっかりと空気を抜く。これを繰り返し、最後は表面を平らにする。
みそ玉を容器に1~2個ずつ詰めて上から手のひらや甲で押してしっかりと空気を抜く。これを繰り返し、最後は表面を平らにする。

11
●表面にふり塩をしてラップを貼り付ける
(10)の表面にふり塩(小さじ1程度・分量外)をする。容器の内側と縁をアルコールできれいにふき、みその表面が空気にふれないようにラップを貼り付けふたをする。
※ふり塩の量は、表面積の広さによって調整する。
(10)の表面にふり塩(小さじ1程度・分量外)をする。容器の内側と縁をアルコールできれいにふき、みその表面が空気にふれないようにラップを貼り付けふたをする。
※ふり塩の量は、表面積の広さによって調整する。

ポリ袋に塩(240g程度)を入れた重石をすると、カビ防止に。
12
●容器を紙で覆って冷暗所で保存・熟成
透明容器の場合は紙で全体を覆う。直射日光の当たらない、冷蔵室以外の涼しい場所におく。湿気が多い場所は避ける。
透明容器の場合は紙で全体を覆う。直射日光の当たらない、冷蔵室以外の涼しい場所におく。湿気が多い場所は避ける。

ホーロー容器などの場合はそのまま冷暗所へ。
13
●約6カ月熟成させれば完成
少し食べてみて、甘みやうまみが感じられたらみその完成。
※でき上がりのみその色みは、各家庭で異なります。
※夏場に仕込んだみそは、熟成期間2~4カ月を目安に、完成までこまめに状態をチェックしてください。
少し食べてみて、甘みやうまみが感じられたらみその完成。
※でき上がりのみその色みは、各家庭で異なります。
※夏場に仕込んだみそは、熟成期間2~4カ月を目安に、完成までこまめに状態をチェックしてください。
完成したら、冷蔵室での保管がおすすめです。酵母の活動を抑え、風味、香りを最良の状態に保てます。
「手作り 少量みそセット」の動画はこちら
【よくある質問】
・「種みそ」って? 入れなくても大丈夫?
みその発酵を促すために入れる酵母が生きているみそのこと。原材料に「酒精」「アルコール」の記載がないものを選びましょう。自分で作った手作りみそでもOK。種みそはみその発酵を促すために入れるので、ない場合は入れなくてもかまいません。
・みそを混ぜるときには、ポリ手袋を着けたほうが衛生的?
人の手にはそれぞれ常在菌が付いており、それがみその味を決めるともいわれています。ご家庭で作って楽しむのであれば、素手で作ってみて。ただし、雑菌はNG! 作る前にはアクセサリー類を外して、しっかり手洗いしてください。
・保存容器は何がよいですか?
プラスチックやガラスの容器で作ると、みその状態がチェックしやすいです。ただ、光を通してしまうため、熟成期間中はみそが変色しないように全体を紙で覆ってください。ホーロー容器、かめなどでもOK。
・天地返しはしなくていいの?
少量みそは天地返しは不要です。熟成中にたまり(みそからしみ出る液体)が上がってきたら、清潔なスプーンなどでみそに混ぜ合わせてください。
手作りみそ「よくあるご質問」はこちら>
【よくある質問】
・「種みそ」って? 入れなくても大丈夫?
みその発酵を促すために入れる酵母が生きているみそのこと。原材料に「酒精」「アルコール」の記載がないものを選びましょう。自分で作った手作りみそでもOK。種みそはみその発酵を促すために入れるので、ない場合は入れなくてもかまいません。
・みそを混ぜるときには、ポリ手袋を着けたほうが衛生的?
人の手にはそれぞれ常在菌が付いており、それがみその味を決めるともいわれています。ご家庭で作って楽しむのであれば、素手で作ってみて。ただし、雑菌はNG! 作る前にはアクセサリー類を外して、しっかり手洗いしてください。
・保存容器は何がよいですか?
プラスチックやガラスの容器で作ると、みその状態がチェックしやすいです。ただ、光を通してしまうため、熟成期間中はみそが変色しないように全体を紙で覆ってください。ホーロー容器、かめなどでもOK。
・天地返しはしなくていいの?
少量みそは天地返しは不要です。熟成中にたまり(みそからしみ出る液体)が上がってきたら、清潔なスプーンなどでみそに混ぜ合わせてください。
手作りみそ「よくあるご質問」はこちら>